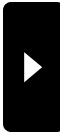2013年08月09日
憂鬱たち

憂鬱たち(金原ひとみ) 文藝春秋 2009
とうの昔に現役横綱より年上となりました。
以前であれば「自分より若造が書いた本など読むものか」なんて息巻いてましたが、そんな事に縛られていたら読む本が無くなってしまう、現に芥川龍之介だって今の私の歳にはとっくに死んでるのです。すげぇな、大人!ちゅうか自分が子供、ちゅうかなんちゅうか…。
そんな芥川龍之介賞、第130回目を弱冠20歳で受賞された金原(かねはら)ひとみさんの短篇集を読みました。あえてふりがなを打ちました、私自身(かなはら)と呼んでいたもので、大人ですから、そう、人の名前は間違えないようにね。因みに同賞は「純文学」で「新人」じゃないといけないみたいです。「純」が付くといってもお酒の出ない、といった意味ではないみたいです。そして勿論、若さゆえの「新人」ではございません。
前置きは長くなりましたが、感想の文章は短いです。意図的ではなくて言葉が思い浮かばなかったので必然的に、ですね。
タイトルの通りとにかく「憂鬱」な短編集なんです、汲めども尽きぬ憂いが溢れかえっているのです、だから鬱がくっついて複数形になって「憂鬱たち」。主人公となる女性が生み出すそんな憂いがネズミ講のように、確変が終わらない裏ロム設定台のように、アレルギー・マーチのように。沢山、連続して、形を変えて、出現します。その様を想像するに、笑うしかなかったのでした、冷ややかに、悲しげに。自虐的でありながらも他殺的な、云わば「鬱の軽躁状態」。そしてこの高速増殖されたかのような憂鬱のメモリー上で繰り広げられるのが愛すべき自己、自己愛の象徴ともいえる「妄想」です。憂鬱と云う名の舞台、そこで繰り広げられるピン芸人のひとりノリ・ツッコミをする様な妄想。このセットで読者の感覚はだんだん麻痺していくことでしょう。なんだかですね、可笑しく思われるかも知れませんが、私はこの状態にこそ人間の生(「性」でも良いかな)を強く感じたのでした…。
って、こんな感じで何とも感想の言い難い本を読んでしまいました。面白かった?気持ち悪かった?いやいや、感想は一言では述べられません。7つの短編が収められています。私の面白かったという意味合いでのオススメは6番目に書かれた「ゼイリ」です。
2011年06月11日
我が家の本棚から 第三回
短命かと思いきや三回目を迎えてしました、このシリーズ。奥さんの本棚から一撮み、それを斜め読みするというコンセプトでやってます。趣味や興味は違えど、結構(私が読んでも)面白い本があるのね。
で、今回はコレ。
田口ランディさんが9名の知識人(?)と色んな事を対談しています。その9人とは・・・、
もちろんナナメヨミですので、とりあえず一人だけ読んでみます。
で、今回私が選んだのは、ヒロシマとアウシュヴィッツの体験から、森達也さんとの対話。
人々が諍い合うことを止める、言うなれば敵対していた相手を理解する手立てとして、森さんは現在のアウシュビッツ捕虜収容所のあり方を引き合いに出して対話を進めています。
一切語られることの無い、加害者とされている人たちの声。ナチスに属しているからとはいえ、鬼ではなくもちろん人間である。彼らも同じく家庭を持ち、妻や両親・子供たちと暮らしているだろう。そんな「普通」とも思える人々がなぜ残虐な行為をしなければならなかったか、そしてどんな思いを抱えてその「場」にいたのだろうか?
ただ被害者の鎮魂を祈るのではなく、同時に加害者とされた人たちの事に言及する、そこにこの負の力を止める鍵があると、森さんは語ります。
そしてヒロシマのあの言葉。「安らかに眠って下さい。過ちは繰り返しませんから」
もともとこの言葉は、あまり好意的に受け止められていなかったようです。被害者(被害国)が発する言葉ではない、ということで。しかし彼はこの言葉を「被害者・加害者の区分ではなく、今を生きるすべての者が原爆で亡くなった方に誓う言葉だ」と捉えています。そしてこのフレーズこそが、「危機管理」と「報復」の連鎖という人類の宿業から抜け出せる可能性を示している、と記されています。
結局、本のタイトルが意味する内容は、この回ではあまり語られませんでした。といいますか、田口さんはあまり積極的に「生きる意味を教えてください」と森さんに聞いていなかったような。それよりも彼の話に
どんどん乗ってきている感がありました。
それと「危機管理」と「報復」の連鎖と言えば真っ先に思いつく、イスラム圏とアメリカを中心とする国々の戦い。全くもって解決の道は遠いようです。すこしでもこのヒロシマの言葉が彼らに響けば…、と強く思った次第でした。
で、今回はコレ。
 | 生きる意味を教えてください-命をめぐる対話 田口 ランディ バジリコ 2008-03-01 Amazonで詳しく見る |
田口ランディさんが9名の知識人(?)と色んな事を対談しています。その9人とは・・・、
藤原新也
内田樹
西垣通
鷲田清一
竹内整一
玄田有史
森達也
宮台真司
板橋興宗
もちろんナナメヨミですので、とりあえず一人だけ読んでみます。
で、今回私が選んだのは、ヒロシマとアウシュヴィッツの体験から、森達也さんとの対話。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
と、ここまで書いて2ヶ月ほど過ぎて、あわてて今日続きを書いています。面白かったので一気に書けるかなぁ、と思っていたのですがなかなか筆が進みません。そんなこんなで滞ってたらビンラディンが殺されちゃうし、ヒロシマの部分で大事な意味合いを持つ慰霊碑の言葉も、村上さんが上手に説明されましたね。
ま、何が言いたいかってーと、「さっさとブログ更新しなさい」ということ。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
人々が諍い合うことを止める、言うなれば敵対していた相手を理解する手立てとして、森さんは現在のアウシュビッツ捕虜収容所のあり方を引き合いに出して対話を進めています。
一切語られることの無い、加害者とされている人たちの声。ナチスに属しているからとはいえ、鬼ではなくもちろん人間である。彼らも同じく家庭を持ち、妻や両親・子供たちと暮らしているだろう。そんな「普通」とも思える人々がなぜ残虐な行為をしなければならなかったか、そしてどんな思いを抱えてその「場」にいたのだろうか?
ただ被害者の鎮魂を祈るのではなく、同時に加害者とされた人たちの事に言及する、そこにこの負の力を止める鍵があると、森さんは語ります。
そしてヒロシマのあの言葉。「安らかに眠って下さい。過ちは繰り返しませんから」
もともとこの言葉は、あまり好意的に受け止められていなかったようです。被害者(被害国)が発する言葉ではない、ということで。しかし彼はこの言葉を「被害者・加害者の区分ではなく、今を生きるすべての者が原爆で亡くなった方に誓う言葉だ」と捉えています。そしてこのフレーズこそが、「危機管理」と「報復」の連鎖という人類の宿業から抜け出せる可能性を示している、と記されています。
結局、本のタイトルが意味する内容は、この回ではあまり語られませんでした。といいますか、田口さんはあまり積極的に「生きる意味を教えてください」と森さんに聞いていなかったような。それよりも彼の話に
どんどん乗ってきている感がありました。
それと「危機管理」と「報復」の連鎖と言えば真っ先に思いつく、イスラム圏とアメリカを中心とする国々の戦い。全くもって解決の道は遠いようです。すこしでもこのヒロシマの言葉が彼らに響けば…、と強く思った次第でした。
2011年05月05日
まつを家の「愛すべき女たち」
最近、うちの奥さんと娘を見ると、駆け引きのようなものが存在するように思える、そう、子育ての中に。なんと言うかなぁ、パワーバランス?母親役を演じている?上手に表現出来ないなぁ、そう、私だけが良く解っていないのだ。
そしてそのつど、あの漫画のこのシーンを思い出してしまう。

愛しい娘なんだけど、無償の愛が溢れることは少し違う親子の縁、なのかな。殊に実生活、現実社会においては。母である以前に、女であり人間でもある、そしてそんな娘も母になる、みたいな。
正調よしなが節の、ホントに痺れる台詞回しである。
単純な男性の私には(男性をひと括りにしたら失礼か)、母と娘の間にある何となく暗~くてアンタッチャブルな部分など理解出来そうもない。そして、たぶんこれは「女の子の不可解さ」としてすべての男子が一番最初に躓くものじゃないかなぁ?
綱渡り的にさえ見える女性社会のバランス感覚。知らぬ間に母から娘へと、生きる為の教えとばかり受け継がれるのだろうか?そこの娘さんたち、ホントにそうなんでしょうか?
解らないことが多すぎる。だけど、一つだけ確かなことがある。それは・・・、
父親だけ理由もわからず蚊帳の外だということ、寂しいけど。
そしてそのつど、あの漫画のこのシーンを思い出してしまう。

愛すべき娘たち (Jets comics) 第一話より よしながふみ
第一話より よしながふみ
愛しい娘なんだけど、無償の愛が溢れることは少し違う親子の縁、なのかな。殊に実生活、現実社会においては。母である以前に、女であり人間でもある、そしてそんな娘も母になる、みたいな。
正調よしなが節の、ホントに痺れる台詞回しである。
単純な男性の私には(男性をひと括りにしたら失礼か)、母と娘の間にある何となく暗~くてアンタッチャブルな部分など理解出来そうもない。そして、たぶんこれは「女の子の不可解さ」としてすべての男子が一番最初に躓くものじゃないかなぁ?
綱渡り的にさえ見える女性社会のバランス感覚。知らぬ間に母から娘へと、生きる為の教えとばかり受け継がれるのだろうか?そこの娘さんたち、ホントにそうなんでしょうか?
解らないことが多すぎる。だけど、一つだけ確かなことがある。それは・・・、
父親だけ理由もわからず蚊帳の外だということ、寂しいけど。
2011年04月14日
我が家の本棚から 第二回
なんか大げさに聞こえるかもしれないので「世界の車窓から」みたいなタイトルにしてみました。大したことは書けませんきませんのでご安心を。
でー、前回は内容だけに重たくなっちゃったので、第二回目は簡単にと私と家内の共通の趣味である「酒」から一冊。お互い好きなので、酒にまつわる蔵書も少なくはないと言えるかもしれません。その中から「作家の酒」という本をご紹介します。
物書きと言われた人たちが愛した酒、行きつけだった店のいつもの肴、家での献立。それらにまつわる文章と写真、近親者の言葉が寄せられています。十人十色、いろんな酒の飲み方があるものです。ちなみに最近の私は、いりこを齧りながら飲むのが一番楽で良いのです。たかがいりこと言いましても、味の仕方がぜんぜん違うんですねぇ。おかげで美味しい出汁もひけるようになりました。
えー、本題に戻りましてっと。知ってる名前では、池波正太郎、中上健次、山口瞳、赤塚不二夫、星新一、大藪春彦などなどなど。みんなグラスや猪口を傾ける時の表情たるや、ただ幸せそうなんて言葉では尽くせぬ、なんとも云えぬ佇まいなのです。
作家それぞれに簡単なコピーが添えられてます、私もこんな酒飲みになりたいものです。
でー、前回は内容だけに重たくなっちゃったので、第二回目は簡単にと私と家内の共通の趣味である「酒」から一冊。お互い好きなので、酒にまつわる蔵書も少なくはないと言えるかもしれません。その中から「作家の酒」という本をご紹介します。
物書きと言われた人たちが愛した酒、行きつけだった店のいつもの肴、家での献立。それらにまつわる文章と写真、近親者の言葉が寄せられています。十人十色、いろんな酒の飲み方があるものです。ちなみに最近の私は、いりこを齧りながら飲むのが一番楽で良いのです。たかがいりこと言いましても、味の仕方がぜんぜん違うんですねぇ。おかげで美味しい出汁もひけるようになりました。
えー、本題に戻りましてっと。知ってる名前では、池波正太郎、中上健次、山口瞳、赤塚不二夫、星新一、大藪春彦などなどなど。みんなグラスや猪口を傾ける時の表情たるや、ただ幸せそうなんて言葉では尽くせぬ、なんとも云えぬ佇まいなのです。
作家それぞれに簡単なコピーが添えられてます、私もこんな酒飲みになりたいものです。
吉田健一 犬が日向ぼっこしているような心境で飲め
池波正太郎 酒を二本ばかり飲んで、また歩きだすのもいい
福田蘭童 うまい魚を食べたきゃ、釣ってこよう
小津安二郎 一升ビン百本空けて一本の脚本が生まれた
田中小実昌 世界中、どこへ行ってもバスに乗り、映画を観たら、酒を飲む
田村隆一 渇くおそれあれば、飲むべし
 | 作家の酒 (コロナ・ブックス) コロナ・ブックス編集部 平凡社 2009-11-25 |
2011年04月09日
妻の蔵書シリーズ(仮)
完全に指宿に引っ越してきて早半月。少しずつですがダンボール箱の山が減ってきております。ほとんどが本、それも嫁さんのもの。彼女は一冊ずつ、丁寧にチェックしてカテゴリー毎に本棚に並べる。しかしまた同じところに並ぶ事が出来ず、また箱の中に戻される奴もあり…。「捨てないで」という声は私に届くべくもなく。行間さえ読めぬ私が解る由もありません。
さて、朝の掃除・洗濯に始まり一日中続くルーティーンワーク。外出は制限され、抱っこしないと寝ない我が子に振り回される。そんな時、まだ隣近所の居場所が定まらぬ、久しぶりに日の目を見た妻の蔵書を手にとって、パラパラと斜め読むのでした。
で、第一回目は昨今の時事ネタをからめつつ…。
ナナメヨミなので著者の言葉ではない巻末の解説文から読んだってもちろん、ぜーんぜん平気なワケである。文章の調子からすぐにお判りかと思うが、「へー、知り合いなんだ」って人が書いてた。この文章の通り、肩肘張らず適度に力の抜けた調子で、本著は記されている。で、読んだのは第7章 危険な日常―若狭湾原発銀座 のくだり。
一言で言えば「呆れた現実」とでもいいましょうか。しかしこれこそが「僕らの住んでいる世界」なのですね。
興味深くグイグイ読み進むんだけど、だんだん嫌な気分にもなってきた。
他、米軍基地問題、諫早干拓問題、横山ノック知事セクハラ事件と、向き合うのが大変な内容がてんこ盛りです。
さて、朝の掃除・洗濯に始まり一日中続くルーティーンワーク。外出は制限され、抱っこしないと寝ない我が子に振り回される。そんな時、まだ隣近所の居場所が定まらぬ、久しぶりに日の目を見た妻の蔵書を手にとって、パラパラと斜め読むのでした。
で、第一回目は昨今の時事ネタをからめつつ…。
からくり民主主義
高橋 秀実
草思社 2002-06
ひとつひとつ章を追って、本書を最後まで読み終えたとき、たぶん僕らはこう思う。なんという困った社会に僕らは生きているのか、と。僕らは腕組みをしたり、頭をかいたりするかもしれない。でも好むと好まざるとにかかわらず、それが僕らの住んでいる世界なのだ。僕らはその中で生きていくしかないのだ。そこからむりに出ていこうとすれば、僕らの行き先は「本当ではない場所」になってしまう。それが結局のところ、この本の結論になるのではないか(たぶん)。
ナナメヨミなので著者の言葉ではない巻末の解説文から読んだってもちろん、ぜーんぜん平気なワケである。文章の調子からすぐにお判りかと思うが、「へー、知り合いなんだ」って人が書いてた。この文章の通り、肩肘張らず適度に力の抜けた調子で、本著は記されている。で、読んだのは第7章 危険な日常―若狭湾原発銀座 のくだり。
一言で言えば「呆れた現実」とでもいいましょうか。しかしこれこそが「僕らの住んでいる世界」なのですね。
虐げられ、生活に困窮した人たちの住処に原発誘致話が持ちかけられる。裏で手薬煉を引くのは福井出身の原子力委員会委員長。用地買収の斡旋から工事まで勤めるのは、その委員長が会長を勤める土木会社。そして彼は科学技術庁長官まで登りつめる。
「建設反対運動は大切」補償金を吊り上げるための交渉術。比率は賛成55、反対45位が丁度良い。反対する人がいないと安全管理をしっかりやってもらえないから。でも原発に頼らざるをえないので賛成が少し多め。
それでたっぷりと補償金をもらう。実際漁で生計を立てていなくても組合員だったら権利を補償してもらえる。
電力会社からの固定資産税等は町税の73%、橋ができ道路ができすべてが整備される。それでも余るお金、過疎化が進む自治体は計画性の無いリゾート開発に費やす。その開発もくだんの土木会社が入っている。他県から人集めが目的の開発なのだが、原発の周りは低人口地帯であることが義務付けされている。
ただ一人まじめに反対している共産党町議。地元の人々は「正しい反対」というらしい。電力会社と地元住民が繰り広げる「虚構の対立」、それを現実とつなぎとめる「潤滑油」的存在なのだと。
自治体では、大事故に備えた防災訓練がこれまで一度も行われていなかった。「町独自の対策は考えていない」と国に身を委ねる町役場の助役。「あの原発が爆発したら日本列島が全滅。そしたらどこに逃げてもしゃあない」と地元の人。
興味深くグイグイ読み進むんだけど、だんだん嫌な気分にもなってきた。
他、米軍基地問題、諫早干拓問題、横山ノック知事セクハラ事件と、向き合うのが大変な内容がてんこ盛りです。
2011年04月03日
荷解きで思い出した事。
このアイコンを憶えておいでの方、どの位いらっしゃるだろうか?
2009年7月を最後に日本版が無くなってしまったEsquire(エスクァイア)のエスキー君なのだ。
前職の頃、この雑誌の毎年4月に出ていた「日本のBAR」という企画は必ず目を通すようにしていた。文章に力があるなぁ、こんなに書けたら良いなぁ、美味い酒飲みたいなぁなどなど思いを廻らして。
どうせ買いに行かなきゃならないからと、来る2002年4月に発行される「日本のBAR2002」に向けて年間購読してた。しかしその企画は結果的に2001年が最後となり、購読も延長することはなくなってしまった。
コラム等も実に熱の篭ったものだったと思う。特に好きだったのが「マグナムが見た21世紀の光と影」と「しゅんのもの歳時記」。
「マグナム~」は毎月2枚、マグナム会員の写真家の作品にいとうせいこうがコラムをつけるというもの。「しゅんのもの~」は、かの魯山人の愛弟子で知られる平野雅章。その時の旬の食べ物を一つピックアップして、様々な文人の俳句を絡めて書かれるエッセイ、唐仁原教久のイラストが添えられる。
2002年あたりまでが面白かったなぁ、ってのが率直な印象。実際、その後「しゅんのもの~」は連載がなくなり、「マグナム~」はいとうのものより明らかに切れ味の鈍い文章が付くようになってしまった。
この業界、広告収入がなければやっていけないのは周知の通り。華々しい広告写真に飾られているんだけど、やっぱり必要なのはエッジの効いた写真や、情報だけではなく"匂い立つ"ような文章だと思う。
こんな時代だからこそ、読者の思いを廻らせたらしむ事、わくわくするような記事を!と願いたいものだ。
2011年04月01日
ブタもおっちゃんも鹿児島には沢山いるのになぁ。
未来ちゃんが届いたばかりなんだけど、次はコレが欲しい。
ブタとおっちゃん 山地としてる
おっちゃんのお腹の上で、安心しきって眠る子ブタ。新聞を読むおっちゃんの後ろから、そっと覗き込むブタ。朝から晩まで、さらには家の中まで。おっちゃんの周りにはいつも、きらきらと瞳を輝かせたブタがまとわりついています。
香川県で養豚場を営み、まるで家族のように1200頭のブタと暮らすおっちゃん。大量飼育・大量生産化に伴い、餌やりから糞尿の処理までどんどん機械化が進む養豚業界で、おっちゃんは自分の手で一頭ずつに愛情を注いでブタを育てます。
養豚農家として、農林水産大臣賞を何度も受賞する程の腕を持ったおっちゃんの養豚場では、単に生産するという域を超えた、愛するものと共に生きる喜びが溢れています。
市役所職員として農林水産行政に携わる中、おっちゃんに出会った著者が10年にわたり撮り続けた、ブタとおっちゃんの家族の記録。2009年に自費出版され、口コミで話題沸騰!その幸せが多くの人の心を震わせた写真集が、さらに味わい深く生まれ変わりました。



有限会社フォイルより引用
1200頭もいて大量飼育・大量生産化に逆行しているとは思えませんが(出版社がちょっと話を盛っとるな)、タバコと缶ビールが似合うおっちゃん、子ブタと一緒の時の表情が素敵です、しっかしウサマに似とるなぁ。
2月にはリトルモア地下で写真展やってたみたい。こんな催し、鹿児島に来ないかなぁ。
2011年02月15日
エロティック・ジャポン

エロティック・ジャポン L'Imaginaire Erotique au Japon
アニエス・ジアール(著) にむら じゅんこ(翻訳)
いやー、またしても衝動買い、しかも高かった。値段に見合う内容かどうかは、各個人の判断にお任せしま~す。どうにかして仏語版が欲しかったのですが(でかくてカラーらしい)、たまたま寄ったアミュの紀伊国屋でみかけちゃいました、それも通常行くはずのない一番右奥辺りでに嫁さんを探している時に。もともと期待していたレゾネっぽいな内容ではなく大量で長いの文字列!読めないフランス語の本買わなくて良かったっス。
内容は、著者であるフランス人女性ジャーナリストが日本の性をストレートに語った評論。文字が多く期待はずれかと思ったんですが、結構噛みごたえのある文章に引き込まれましたよ、半ば強引ですが。日本人が持つ特有の価値観や美学をまったく取っ払った形で、ガツンとこの手の題材を見せられるとちょっとビビリます。だけど面白い事に、それで「気付き」が起こったりするわけです。自分の意識してなかったフェティズムを突然認識させられたり。
全体の文章の雑さ、洋書ならではの日本語訳のニュアンスが気になる所などあったんですが、最後の訳者のあとがきを読んで膝を打ちましたよ。著者の極端な日本の認識を上手に訳し直し、かつ比較文化的な側面を壊さぬよう不自然なテキストをあえて残し違和感のある文章にしてあるようです。この匙加減は理解出来そうも無いけど凄い事だってことはわかりますよ。
数多くの側面から箇条書きされたこの本、著者は総括するような文章を残しておりません。フランス人の為の日本性風俗百科とでも言いましょうか?内容は兎も角として、この本がフランスで沢山売れている事に何かがあるのでしょう。彼らが日本の何かに強い欲求を持ち、私たちは多少の誤解を受けながらも発信し続けているのです。
中で紹介されていた作品を(好みで)抜粋してご紹介致します。
まずはカバー絵として取り上げられている「月の沈むまで」が収められた「ナルシスの祭壇」。ご自身のホームページのトップページにも使用されています。(解りにくい!股間のバラをクリック)いやー、美しい、ゾクゾクしますねぇ。この絵に誘われて本題の書を買った人、少なくはないはずです。でもなかなかこの画集をポチッっとする勇気がありません、家人に見られたら・・・、人間が小さいのです。
日本酒業界では特に知名度があるはず、高井株式会社の痴虫のラベルでおなじみの作家さんです。独特の作風は早くから海外で注目され、多数の作品集も発売されています。春画、江戸というより昭和、何か一抹のノスタルジーを感じさせてくれます。この「あかいはこ」から数点紹介がありました。
会田誠氏の1997年の作品、実は私まだ読んだ事がありません。アニエス・ジアールは、太平洋戦争に敗北し日本人男性性の自尊心が失われたと述べ、その一つの要素として同書を紹介しています。ですがあくまでも一つの要素として。ここで彼女は、日本人男性にとって一番大切だったものを別に紹介しています。なかなか面白い文章ですので是非読んでみて下さい。
世界でも類を見ない、百花繚乱の如き性産業が介在する日本、この現実をまとめ上げる事は日本人でも容易な事ではありません。ただ個別の職種紹介となってしまった第10章、ここで紹介されていたこの本に原点を読み取る事が出来るかも知れません。「性風俗の歴史を知らずにキレイ事を語る者は本書を読むといい。そこには人が人であることの切なさや愛らしさが見えてこよう。」この帯の言葉はグッっとくるものがあります。
最後に紹介されてた絵と写真を少し。
森口裕二


トランク 遠い遠い夏の日
木村了子


Beauty of my dish 桜下男体刺身盛り
月飛行 おいらん道中図


Beauty of my dish 私のケーキ皿
人魚達の宴図
島隆志


田亀源五郎


その他



小林永濯 天瓊を以て滄海を探るの図
上田風子 マドンナの真珠
橋口五葉 湯浴の女


金井清顕 スーパーソリス 吉田良 人形
2011年02月12日
未来ちゃんが帰ってくる!

写真集『未来ちゃん』
写真:川島小鳥 装丁:祖父江慎
佐渡に住む未来ちゃんの春夏秋冬、一年間を収めた写真集。前作より内容の濃いものになっているようです。今回はどんな表情を見せてくれるのでしょうか?楽しみです。発売は3月との事。
2011年02月10日
Rosso ITALIANO ~カンパリ色のイタリア~
 Rosso ITALIANO:カンパリ色のイタリア (ストリートデザインファイル)
Rosso ITALIANO:カンパリ色のイタリア (ストリートデザインファイル)坂本 きよえ(著) 都築 響一(編集)
もう飲りましたか「処女の味」?1970年代初頭、カンパリの輸入代理店ドッドウェルはイタリアの赤い液体をこう評しました。当時の日本洋酒文化が垣間見えるコピーです。従価税等で高価であった輸入酒の敷居は高く、その価値に見合うだけのコピー・グラフデザインが与えられています。この風潮は海外ではむしろ当たり前の事、一流のアーティストが手がけているのでした。
モードの都ミラノで生まれたカンパリ、その存在を世界に知らしめたデザインを収めた一冊。
何も無い時代に生まれたデザインには、ポストモダンな世の中に手本となる何かがあるのではないでしょうか。




この本に載っているカンパリソーダ(画像右)のベンディングマシンが欲しいのです、1930年代の。といっても中に入れるカンパリソーダが日本では販売されてないんですけど。昔売ってたのになぁ、現在イタリア・スイス・オーストリア・ドイツだけで販売中との事、ちなみにイタリアでは1本0.7€(78.694円)だそうです。そんなもんだよねぇ。これで冷蔵庫を真っ赤に埋め尽くしたい。お祭りの露店で売ってたら素敵だなぁ。どなたかイタリアに行かれる方いませんか?100本ほど買って来て下さい、お願い致します。
さて色々調べてたら本で紹介されているカンパリの映画CM(←時代だなあ)を見つけましたのでご紹介致します。アニメーションから音楽のセンスに至るまで、非常に質の高いものだと感じます。1960~70年代生まれは
CGやら3Dなどよりも、最後はここに帰ってくるものなのでしょう。時代が近いせいか、出てるキャラクターがアンクル・トリスに何となく似てますね。
(c) Fondazione Cineteca Italiana
Italy ca. 1960
Director: Nino Pagot, Toni Pagot
Alternative title: Rapsodia Campari